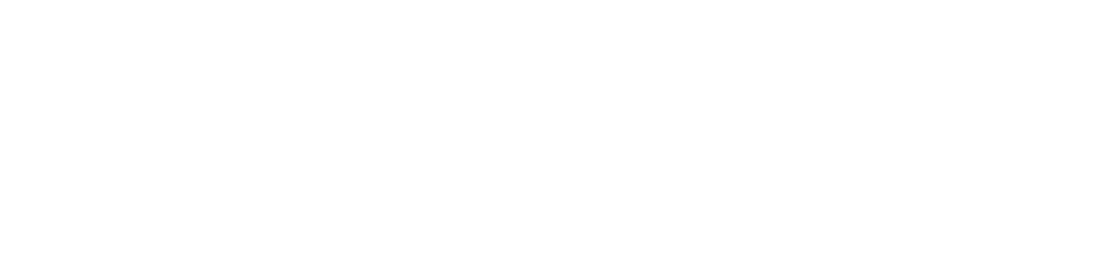DESIGNING SOCIETY
社会をデザインする
多様な人々が「違い」によって否定されることなく、生活していくことのできる社会構築の方法が求められています。
社会学部では、いま起こっている社会問題の原因を分析し、解決していくための方法を探っていきます。
人間の多様性を理解する力は、意図的に訓練を行わなければ身につきません。
対話と相互理解を目標とするコミュニケーションのスキルを磨いていく必要があります。
社会学部では、大学4年間での教育と訓練を通じて「多様な存在である個人」を理解し、尊重することができ、
実際に社会問題を解決していく方法を考案できる実践力のある人材の育成をめざしています。
社会学部では、いま起こっている社会問題の原因を分析し、解決していくための方法を探っていきます。
人間の多様性を理解する力は、意図的に訓練を行わなければ身につきません。
対話と相互理解を目標とするコミュニケーションのスキルを磨いていく必要があります。
社会学部では、大学4年間での教育と訓練を通じて「多様な存在である個人」を理解し、尊重することができ、
実際に社会問題を解決していく方法を考案できる実践力のある人材の育成をめざしています。
FACULTY MEMBERS
教員紹介
やりたいことにいろいろチャレンジしてみましょう!
私は「図書館情報学」を専門としていますが、きっと皆さんにとっては、初めて聞く学問名称だと思います。「図書館情報学」は、図書館自体を研究対象とするだけでなく、資料の収集・保存、利用に関する事柄や、情報の利用やあり方などについても研究する学際的な学問領域です。
本学では『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』の資格課程で「図書館情報学」を学ぶことが出来ます。これらの資格は「図書館法」「学校図書館法」に定められた国家資格であり、本学の所定の単位を修得することで取得できます。
資格は一生涯有効ですので、卒業時にたとえ図書館に就職しなくても結婚・出産・転居・転職といった人生の岐路で就職先として常に図書館を選択肢の一つとして考えることもできます。4年後だけでなく人生のキャリアプランも考慮してぜひ『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』の資格取得にチャレンジしてほしいと思います。
『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』を目指すには、もちろん本が好きな事も大事な要件ですが、資料を知り利用者を知り、その「資料」と「利用者」を結ぶ付けることが大きな役割でもあります。そのためには利用者とも気軽に会話ができるコミュニケーションも大いに重要です。「読書が好き」、「図書館が好き」「コミュニケーションが好き」「情報学に興味がある」という学生さんがいれば、ぜひこれらの資格課程を受講してみてください。
本学では『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』の資格課程で「図書館情報学」を学ぶことが出来ます。これらの資格は「図書館法」「学校図書館法」に定められた国家資格であり、本学の所定の単位を修得することで取得できます。
資格は一生涯有効ですので、卒業時にたとえ図書館に就職しなくても結婚・出産・転居・転職といった人生の岐路で就職先として常に図書館を選択肢の一つとして考えることもできます。4年後だけでなく人生のキャリアプランも考慮してぜひ『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』の資格取得にチャレンジしてほしいと思います。
『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』を目指すには、もちろん本が好きな事も大事な要件ですが、資料を知り利用者を知り、その「資料」と「利用者」を結ぶ付けることが大きな役割でもあります。そのためには利用者とも気軽に会話ができるコミュニケーションも大いに重要です。「読書が好き」、「図書館が好き」「コミュニケーションが好き」「情報学に興味がある」という学生さんがいれば、ぜひこれらの資格課程を受講してみてください。
閉じる
部屋を片付けていたら、自分が大学1年生だった時の「レポート」が出てきました。手書きのプリントでした。当時の私は、一体どんなことを書いたのか、改めて読んでみました。すると、現在の自分と全く同じ「考え」が書かれており、自身の普遍的な「根幹」になっていることを再認識しました。学生の皆さんにとって、この4年間の大学生活は、今後の長い人生の「基盤」をつくる、とても大切な時間だと思います!
閉じる
何かを「理解する」ことは、理解する前と後で自分が全く変わるということだ。そう言った人がいます。何かを理解したことによって、世界をみる眼差しが根本から作り替えられる。それは自我を揺るがすような体験になる、というわけです。ちょっと怖いような気もしますが、自分を揺さぶるような「理解」に到達することはきっとワクワクする体験になるはずです。みなさんが本学で心躍る「理解」を獲得できるよう願っています。
閉じる
「違い」が「分断」を生まない社会を目指して
お互いが異なる存在であることを認めあうことは、実はとても難しく、知的な訓練を必要とします。関わりを避けることの方が、簡単で本能的な反応でしょう。でも、「避けること」が集団で行われたらどうなるでしょうか。「排除」とか「隔離」といった言葉で示される社会状態とは、実はこんな個人レベルの「よく分からないから避けておこう」という選択の集積によって作られています。
こうした選択を避けるためにはどうすればよいか。学校や地域におけるバリアフリー教育について考えることも、大切な取り組みです。
人間の多様性を理解する力は、意図的に訓練を行わなければ身につきません。対話する力と、相互理解を目標とするコミュニケーションのスキルを磨いていきましょう。
こうした選択を避けるためにはどうすればよいか。学校や地域におけるバリアフリー教育について考えることも、大切な取り組みです。
人間の多様性を理解する力は、意図的に訓練を行わなければ身につきません。対話する力と、相互理解を目標とするコミュニケーションのスキルを磨いていきましょう。
閉じる
パソコンの操作が上手な人でも、パソコンがどのようにしてうごいているのかという「仕組み」まで理解している人は少ないでしょう。「仕組み」を知らないままでは、故障したときに対応できません。社会についての知識も同じです。変化の激しい時代では、昨日まで通用していた「操作方法」が使えなくなることが多くあります。この事態に対応するためには、社会の「仕組み」を知らなければなりません。そんな「仕組み」を学ぶ社会学を一緒に勉強しましょう。
閉じる
「自分はこれに取り組んだ!」といえるようなものを大学生活4年間で1つつくろう
大学生活は長いようであっという間に終わってしまいます。何か1つでも意識をもって取り組めるといいですよね。そういう私は大学時代ダンスサークルに打ち込んでいました。その時に学んだことはできないことを恥ずかしがらずにみんなの前で努力していくという事です。勉強や学問も同じだと思っています。このくらいでいいやと思っていると本当にそこまでしか伸びません。手足をもう一歩大きく外に広げて、少し大きく踊れるように努力していくと、大学4年間で本当に伸びていきます。皆さんが成長していく姿が見られることを楽しみにしています。
閉じる
よく学び、よく遊んで、充実した大学生活を!
大学時代は、みなさんの人生のうちで「自分のために自由にたっぷり時間を使える」最初で最後の時期です。「大学に入学したらやりたいこと」をいろいろと考えてみてください。そして、大学での4年間は、その「何か」にどんどんチャレンジし、打ち込んでみてください。学ぶために大学に入学するのですが、大学の勉強だけではもったいないです。よく学び、よく遊んで充実した大学生活をすごしてください。
閉じる
何事にも目的意識を持ってぶつかっていってください。何となく大学に入って,4年経ったから卒業するのでは全く意味はありません。あまり苦労したくない,楽をして何とかしたいと思っていたら大間違いです。目的を持った人間と持たない人間では,その結果は自ずと明らかです。うまくいかなかったからといって,他人のせいにしてはいけません。どうか人生の目標を設定し,失敗を怖れず積極的にチャレンジしていってください。
閉じる