卒業論文
卒業論文執筆の過程では、現代社会の多様な社会問題や現象に対して、独自の視点から問いを立て、その解法を見いだしていきます。
論文作成にあたっては、先行研究を調べつくすことから始まります。
先人が積み上げてきた「知」と真正面から向き合うことが第一歩となります。
そして「この研究は何のために行うのか」「この研究はどこに独自性があるのか」など、自らのリサーチ・クエスチョンを問い直すことが求められます。
こうした問いと調査・考察を繰り返すことによって、新たな「知」が生み出されていくのです。
社会学部では、この一連の過程に挑戦した証となる「卒業論文」に大いなる価値を置いています。
主な卒業論文題目一覧
24年度卒業生
- 「家具の音楽」からLofi Hiphopへ―音楽の背景化への模索とその到達点―
- “尊厳ある最期”の迎え方―全世代型セルフ・ネグレクトと一億総多死社会を見据えて―
- 長時間労働がもたらすキャリア形成の壁―ジョブシェアリングでワーキングママが休みやすい社会へ―
- フードバンクによる多面的支援―橋渡しによる地域共助の実現―
- 現代の子どものための「コドモラル」―「校則」に代わる新たなルールの形―
- 駅周辺における喫煙所設置の必要性―JR横浜線沿線駅を事例に―
- 児童福祉施設入所児童の進学に向けてどのような支援が求められているか?―大学進学を主たる観点として―
- 高齢者の孤立死に関する社会的要因と対策―孤立を防ぐためのコミュニティづくり―
- 日本の非核武装と世界から核兵器を無くすために―日本がとるべき行動について―
- 「全世代型社会保障」の実現における消費税の意義
- 山間の町の技能実習生―彼らを支える会津工場と只見町明和地区の地域資源―
- 教師が生徒に与える影響について―教師期待効果と隠れたカリキュラムからの考察―
- 課題遂行中のモチベーションのダイナミズム―部署間協働課題における承認欲求の検証―
- 障害者の入所施設からグループホーム、そして一人暮らしへの移行―自己決定による自立―
- 競馬場のエスノグラフィー―競馬の歴史と現地での観察―
- “森里海連環の視点から見た「牡蠣の森を慕う会」の環境保全活動の意義と展開―気仙沼湾における実践を中心に―”
23年度卒業生
- 東京五輪1964年・2020年が与えた地域活性化への影響の違い ―藤沢市での取り組みの比較―
- 不可視化された働く父親の悩み ―男性育児休業がもたらす波及効果―
- 結婚は幸せになる1つの手段 ―若者の意識改革と結婚への積極的プロセス―
- 外国人労働者が増加する日本で取り残される子どもたち ―外国にルーツを持つ子どものためのキャリア教育と仕組みづくり―
- 正義とは何か ―映画で紐解く正義―
- 学校教育におけるジェンダーバイアスの状況 ―教科書の分析を通じて―
- 東日本大震災から考える地域活性とは ―宮城県石巻市を事例に―
- ヤングケアラーである子どもたちを早期発見するには?
- 中高年層と高齢者の社会的孤立に関する比較研究
- 障害と刑事責任能力 ―責任主義の考え方―
- 四川省における貧困の現状と対策についての研究
- プレイパークはなぜそこにあるのか ―運営者の活動にかける思いに目を向けて―
- 外国ルーツの子どもと就学前言語教育 ―家庭環境とICT活用の可能性に着目して―
- 教員の働き方に対する世論の変化 ―教員の働き方に関するマスメディアの報道の変化を通して―
- 「生殺与奪ゲーム」の開発と第三者罰実験への適用 ―他者行動に対する罰付与行動効果の実験的研究―
- 学校に求められるスクールソーシャルワーカーとは ―子どものより良い環境をつくるための3つの提案―
- 高校国語における小説の学習機会の減少について ―今後、国語科に求められるものとは―
- 日本ウナギの資源回復に放流事業は適切か ―浜名湖発親ウナギ放流連絡会を事例に―
22年度卒業生
- なぜおじさん構文は気持ち悪いのか
- ひとり親の子どもの貧困―現状と解決に求められるものとは―
- ネット恋愛の可能性―マッチングアプリで未婚化・晩婚化を食い止めろ!!―
- 教員における「競争のすゝめ」―フィンランド教員雇用からの考察―
- 交通空白地域におけるデマンドバスの有効性―神奈川県足柄群中井町を事例に―
- LGBTQの子どもと学校制服の性的多様性について
- 野球人口の減少と野球人気の変化
- 日本における高齢期の貧困問題の課題と展望
- 顔型と髪型の適合性とその対人魅力の実証的研究
- 食品ロスを削減するには―フードバンクや企業の取り組みを事例に―
21年度卒業生
- コロナ禍は睡眠にどのような変化をもたらしたか -アテネ不眠尺度を用いた実証的研究-
- 絵本とオノマトペのつながり
- 空き家の適切な流通と利活用方法 -新しい生活様式によって可能になる他拠点居住の薦め-
- 高齢者のデジタル・デバイド -デジタル化に取り残されないために-
- 女性受刑者の出所後の課題の考察 -受刑中と出所後の支援をつなげるには-
- 戦争体験者の減少が平和教育に与える影響と第四世代への平和教育 -満蒙開拓平和祈念館の取り組みに着目して-
- 日本の福祉行政における専門職の意味 -横浜市とスウェーデンの福祉職採用を手がかりにして-
- 本当に代替要員がいないのは職場?家庭? -仕事と家庭をめぐる時間意識でみえてくる理想のワーク・ライフ・バランス-
- 妖怪をコンテンツとした観光まちづくりについて -調布市を事例にして-
- 洋上風力発電における希望と課題 -日本は洋上風力発電大国となりうるのか-
20年度卒業生
- お笑い芸人がテレビの世界で生き残る方法とは
- 生活保護とバッシング―生活保護受給者はなぜ特別視されるのか―
- デジタルネイティブ世代の新しい家庭生活―インターネットをサポートアイテムに効率的な暮らしを―
- 酒蔵を核としたまちづくり―日本酒はまちづくりの地域資源になりうるのか―
- 大阪市のインバウンド集客の成功例から見る横浜市のインバウンド集客の課題
- 学校に行くことが不登校の子どもたちのゴールなのか
- 指定管理者制度や複合施設は図書館に必要なのか―今日の図書館の在り方を考える―
- 低栄養状態によるリスクと食事支援
- 日本の死刑制度の現状と課題―死刑の抑止力の有無について―
- 鳥肌が立つ楽曲はどのように構成されているか?―テンポ・メロディ・歌詞と身体反応の関係―
19年度卒業生
- アニメ『ルパン三世』からみる表現規制の変容
- 高齢者における回想法の可能性―コミュニケーションを生かした生きがいづくり―
- 少子高齢化を乗り越えるための攻略法―コミュニティで助け合う新しいつながり―拡張家族」―
- 子どもへの食育の重要性について
- 同質化社会と教育―現代社会に潜む日本人の同調行動―
- 第一印象の形成要因と変容条件に関する実証的研究
- スマートフォン遮断実験における不快指数の変化
- インクルーシブ教育が肢体不自由児の社会性の発達に与える影響―今後のインクルーシブ教育に求められる役割とは―
- グローバル社会の発展と終身雇用システムの限界
- 海洋プラスチック汚染に対してどのような対策・課題があるのか―我々の生活への影響を通して―
社会調査演習報告書
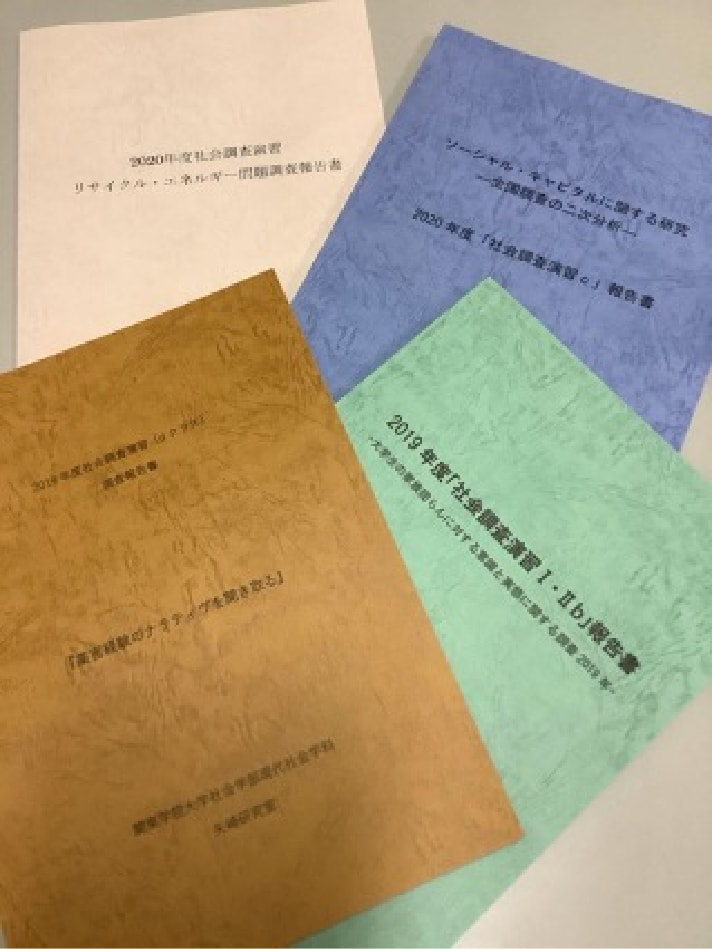
テーマ
- 『世界のウチナーンチュ大会と移民の民族的アイデンティティ』(2023年度)
- 『プラスチックごみと共進的な持続可能性』(2023年度)
- 『世田谷区における住民と地域との関係―「地域生活とコミュニティに関する調査」の二次分析』(2023年度)
- 『不登校支援の市民活動に関する調査報告書』(2024年度)
- 『町内会・自治会の持続可能性の検討―横浜市関ヶ谷自治会を事例に―』(2024年度)
番組制作実績
2024年度作品
過去の作品
- おじさん構文〜なぜ気持ち悪いのか?
- 関内に関東学院大学キャンパスオープン〜知の拠点へ
- 黄金町〜暗黒街からアートとともに生きるまちへ
- 学生と音楽サブスク〜なんでサブスクを使うの?
- 横浜で一番目と二番目に高い山、大丸山と円海山に登ろう
- オタクに魅せられて〜鉄道制服オタクに密着
- 貧乏旅〜青春18きっぷで横浜から博多までケチケチ旅をしてみた
- フードバンクかながわに密着
- 情けは人のためならず。めぐりめぐって社会がため〜子ども食堂運営者・和田信一〜
- 「てげでけ」で、いっちゃが?〜宮崎の方言に見る、県民性の魅力
- 大解剖!タイの緑茶が甘いわけ
- 象使いへの道(ラオス編)
- ミニシアターの歴史とこれから
- 早起きの方法を考えろ!
- 真相解明!! 座席の位置で成績は変わる!?
- 脳内ポイズンベリー
NEXT CONTENTS
学びマップ
