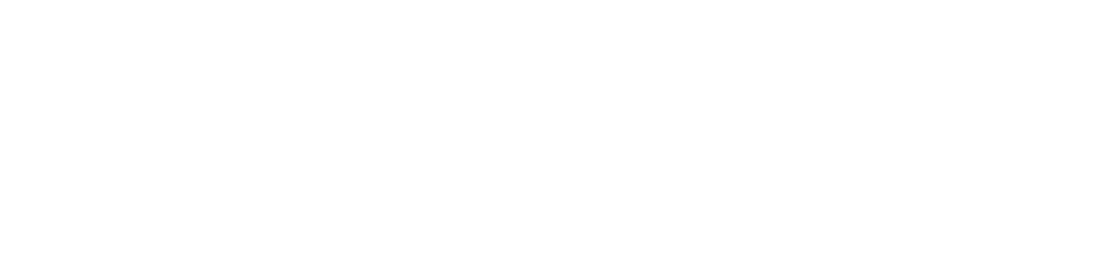DESIGNING SOCIETY
社会をデザインする
多様な人々が「違い」によって否定されることなく、生活していくことのできる社会構築の方法が求められています。
社会学部では、いま起こっている社会問題の原因を分析し、解決していくための方法を探っていきます。
人間の多様性を理解する力は、意図的に訓練を行わなければ身につきません。
対話と相互理解を目標とするコミュニケーションのスキルを磨いていく必要があります。
社会学部では、大学4年間での教育と訓練を通じて「多様な存在である個人」を理解し、尊重することができ、
実際に社会問題を解決していく方法を考案できる実践力のある人材の育成をめざしています。
社会学部では、いま起こっている社会問題の原因を分析し、解決していくための方法を探っていきます。
人間の多様性を理解する力は、意図的に訓練を行わなければ身につきません。
対話と相互理解を目標とするコミュニケーションのスキルを磨いていく必要があります。
社会学部では、大学4年間での教育と訓練を通じて「多様な存在である個人」を理解し、尊重することができ、
実際に社会問題を解決していく方法を考案できる実践力のある人材の育成をめざしています。
FACULTY MEMBERS
教員紹介
大学生のときにしかできないことが、たくさんあると思います。社会人として働くようになると、「大学時代にやっておけば・・・」と後悔することが、多かれ少なかれ出てくるものです。大学に籍を置いて、豊富な時間、何でも話せる友人、自分の関心事に応えてくれる教員などを手に入れ、やりたいことを積極的にやってみてください。
閉じる
「違い」が「分断」を生まない社会を目指して
お互いが異なる存在であることを認めあうことは、実はとても難しく、知的な訓練を必要とします。関わりを避けることの方が、簡単で本能的な反応でしょう。でも、「避けること」が集団で行われたらどうなるでしょうか。「排除」とか「隔離」といった言葉で示される社会状態とは、実はこんな個人レベルの「よく分からないから避けておこう」という選択の集積によって作られています。
こうした選択を避けるためにはどうすればよいか。学校や地域におけるバリアフリー教育について考えることも、大切な取り組みです。
人間の多様性を理解する力は、意図的に訓練を行わなければ身につきません。対話する力と、相互理解を目標とするコミュニケーションのスキルを磨いていきましょう。
こうした選択を避けるためにはどうすればよいか。学校や地域におけるバリアフリー教育について考えることも、大切な取り組みです。
人間の多様性を理解する力は、意図的に訓練を行わなければ身につきません。対話する力と、相互理解を目標とするコミュニケーションのスキルを磨いていきましょう。
閉じる
みなさんは、何か好きなことがありますか。私は漫画を読むのが好きです。何かしら漫画を読んだらその魅力を人に知ってほしいと思います。そんなとき、その漫画のことを要約しながらどの辺がおもしろいのか興味を持ってもらえるよう工夫して話さなければ伝わりません。そのようなことを繰り返しているうちに、何かについて分析したり説明したりすることに慣れていきました。実は、これらは研究活動や授業を行ううえで大切なことです。一見、学業や仕事に関係ないと思われることも繋がっていることがあります。大学ではいろいろなことや人に出会います。何事も「関係ないから」と考えて遠ざけるのではなく、いつかどこかで繋がるという意識を持ってまずはやってみて下さい。そのためのサポートは惜しみません。
閉じる
自由に考えてみよう!
大学という環境は高校までとは大きく異なります。その一つは自由であるということでしょう。自分自身で考え、判断し、行動することができるという自由です。実はこれはとても難しいことです。大学には、「自由に考える」時間があります。これまで自分が正しいと思ってきたことに疑いをもってみましょう。意外にも正しいと思っていたことが違っていることに気づくかもしれません。意見交換ができることを楽しみにしています。
閉じる
私が主な研究対象としている「貧困」とは、生きるために必要とされる様々な「モノ」が、恒常的に不足・欠乏し、生活に困窮した状態のことをいいます。現代社会においては、必要な「モノ」は、お金を払って購入することが一般的であるので、貧困を、まずは「お金がない」状態として理解することもできます。だから貧困についての研究は、わたしたちが暮らすこの社会の中に、なぜ必要な「モノ」を買う「お金」がない人が生み出されてしまうのかについて考えることから始まります。そして、貧困におかれた状態が長期にわたった場合、その状態にある人々にとっては、不安定な健康状態や精神的ストレス、生活習慣の解体、あるいは十分な教育が受けられない等、様々な生活問題をひきおこすことがあります。貧困についての研究は、生活に困窮した人々が様々なかたちで直面する苛酷な状況に焦点を当て、どのようにすればその状況は改善されうるのかを問い直す作業であるという側面を必然的にもつことになります。
貧困という「問題」へのアプローチの仕方には様々なものがあると思いますが、とりわけ私が興味を持って考えているのは、先進国の一員として「豊か」になったはずのわが国において、しかも誰もがそれを「解決すべき」とか「なくなってほしい」と考えている(はずである)にも関わらず、なぜいまだに貧困が存在し続けているのか、ということです。このことについては、ぜひみなさんとも一緒に考えていきたいと思っています。
貧困という「問題」へのアプローチの仕方には様々なものがあると思いますが、とりわけ私が興味を持って考えているのは、先進国の一員として「豊か」になったはずのわが国において、しかも誰もがそれを「解決すべき」とか「なくなってほしい」と考えている(はずである)にも関わらず、なぜいまだに貧困が存在し続けているのか、ということです。このことについては、ぜひみなさんとも一緒に考えていきたいと思っています。
閉じる
パソコンの操作が上手な人でも、パソコンがどのようにしてうごいているのかという「仕組み」まで理解している人は少ないでしょう。「仕組み」を知らないままでは、故障したときに対応できません。社会についての知識も同じです。変化の激しい時代では、昨日まで通用していた「操作方法」が使えなくなることが多くあります。この事態に対応するためには、社会の「仕組み」を知らなければなりません。そんな「仕組み」を学ぶ社会学を一緒に勉強しましょう。
閉じる
やりたいことにいろいろチャレンジしてみましょう!
私は「図書館情報学」を専門としていますが、きっと皆さんにとっては、初めて聞く学問名称だと思います。「図書館情報学」は、図書館自体を研究対象とするだけでなく、資料の収集・保存、利用に関する事柄や、情報の利用やあり方などについても研究する学際的な学問領域です。
本学では『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』の資格課程で「図書館情報学」を学ぶことが出来ます。これらの資格は「図書館法」「学校図書館法」に定められた国家資格であり、本学の所定の単位を修得することで取得できます。
資格は一生涯有効ですので、卒業時にたとえ図書館に就職しなくても結婚・出産・転居・転職といった人生の岐路で就職先として常に図書館を選択肢の一つとして考えることもできます。4年後だけでなく人生のキャリアプランも考慮してぜひ『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』の資格取得にチャレンジしてほしいと思います。
『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』を目指すには、もちろん本が好きな事も大事な要件ですが、資料を知り利用者を知り、その「資料」と「利用者」を結ぶ付けることが大きな役割でもあります。そのためには利用者とも気軽に会話ができるコミュニケーションも大いに重要です。「読書が好き」、「図書館が好き」「コミュニケーションが好き」「情報学に興味がある」という学生さんがいれば、ぜひこれらの資格課程を受講してみてください。
本学では『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』の資格課程で「図書館情報学」を学ぶことが出来ます。これらの資格は「図書館法」「学校図書館法」に定められた国家資格であり、本学の所定の単位を修得することで取得できます。
資格は一生涯有効ですので、卒業時にたとえ図書館に就職しなくても結婚・出産・転居・転職といった人生の岐路で就職先として常に図書館を選択肢の一つとして考えることもできます。4年後だけでなく人生のキャリアプランも考慮してぜひ『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』の資格取得にチャレンジしてほしいと思います。
『図書館司書』や『学校図書館司書教諭』を目指すには、もちろん本が好きな事も大事な要件ですが、資料を知り利用者を知り、その「資料」と「利用者」を結ぶ付けることが大きな役割でもあります。そのためには利用者とも気軽に会話ができるコミュニケーションも大いに重要です。「読書が好き」、「図書館が好き」「コミュニケーションが好き」「情報学に興味がある」という学生さんがいれば、ぜひこれらの資格課程を受講してみてください。
閉じる
何かを「理解する」ことは、理解する前と後で自分が全く変わるということだ。そう言った人がいます。何かを理解したことによって、世界をみる眼差しが根本から作り替えられる。それは自我を揺るがすような体験になる、というわけです。ちょっと怖いような気もしますが、自分を揺さぶるような「理解」に到達することはきっとワクワクする体験になるはずです。みなさんが本学で心躍る「理解」を獲得できるよう願っています。
閉じる